刑事事件の流れ
公開日2022/03/29
更新日2022/07/14
カテゴリ刑事事件の基礎知識ファイル

刑事事件の加害者となった場合、不利益を最小限に抑え、早期解決を目指すには、できるだけ早く釈放や不起訴につながる行動を起こすことが大切です。
今回は逮捕された場合なぜ早く行動を起こすべきなのか解説していきたいと思います。
【この記事のポイント】
- 逮捕から勾留されるまでの流れがわかる
- 起訴から刑事裁判開廷までの流れがわかる
【逮捕後48時間以内】警察の取り調べ
一般的に逮捕されることは、「犯罪者である」というイメージを持っている方は少なくないと思います。
しかし、逮捕は「犯罪行為をした」という強い嫌疑がかかっている状態であって、その時点で有罪かどうかが決まっているわけではありません。
逮捕は逃亡や罪証隠滅のある被疑者に対し、行われる捜査の一環です。
警察は取り調べのうえ犯罪行為をした疑いが強いと判断した場合には、逮捕後48時間以内に検察に被疑者の身柄送致を行う必要があります。
これは刑事訴訟法203条1項にも定められています。
なぜ48時間以内に行わなければならないのかというと、長期間の拘束は憲法に定められている「身体の自由」に反するためです。
つまり、48時間以内に犯罪の嫌疑が晴れれば、釈放してもらえることもあります。
【身柄送致後24時間以内】検察の勾留決定
警察から身柄送致をした場合、検察は24時間以内に被疑者の勾留請求を行うかどうかを決める必要があります。
勾留は、引き続き捜査機関が取り調べをしたいけれど、釈放すると「逃亡」や「罪証隠滅」の疑いがある被疑者に対して行う手続きです。
検察が勾留請求を行い、裁判所が実際に被疑者と面談を行って勾留決定するかどうかを決めます。
勾留請求が決定されると原則として10日、最大で20日間の身柄拘束をされる恐れがあります。
そのため勾留を回避したいと思うのであれば、裁判所が勾留決定を行う前に「意見書」等を提出し、「勾留の必要性はない」ということを納得してもらう必要があります。
しかし、逮捕後、勾留決定がくだされるまでは、国選弁護人を選任することはできず、また家族等との連絡や接見(面会)も許されません。
逮捕後から勾留決定までのあいだ行動を起こす場合には、家族等に対応してもらい、私選弁護人を選任する必要があります。
【勾留決定後20日以内】検察が起訴するかどうかを決める
裁判所が勾留決定を行うと、被疑者は基本的に拘置所といって、法務省が管轄される施設に収監されます。
検察官は基本的に最大で10日間、引き続き捜査の必要があるとした場合には、更に10日間のあいだに被疑者を起訴するかどうかを決めます。
起訴とは、公訴の提起といって、「刑事裁判を開くかどうか」のことで、検察官のみが持つ権限です。
なお、日本の司法では、起訴された場合の有罪率は99パーセントといわれており、勾留期間中に不起訴処分を得られないと前科がつく可能性が非常に高くなります。
不起訴処分は、捜査機関への取り調べにおける対応に注意しなければいけなかったり、被害者の方がいる場合には示談を成立させたりすることによって得やすくなります。
しかしながら、被疑者自身は拘置所等に収容されているため、自力で示談交渉等を行うのはほぼ不可能といっていい状態でしょう。
そのため、自分で私選弁護人に依頼するか、国選弁護人に対応をお願いすることになります。
国選弁護人を選任した場合、自分自身が望む弁護士を選任できるわけではありません。
また、弁護士によっては事件に対する対応の仕方がまちまちです。
したがって、不起訴処分を得たいと強く希望するのであれば、私選弁護人に弁護を依頼した方が得策です。
【起訴決定後1か月半~2か月】刑事裁判が開かれるまでの被告人勾留
検察官が起訴を決めた場合、呼称が被疑者から被告人に変わります。
被告人となって、逃亡や罪証隠滅の疑いがある場合には、引き続き勾留されることになります。
起訴後、身柄の釈放を望む場合には、裁判所へ保釈請求の手続きを行う必要があります。
保釈請求が通るためには、逃亡や罪証隠滅の恐れがないこと、身柄引受人がいること等を裁判所に示す必要があります。
また、保釈金を裁判所に支払う必要もあります。
保釈金は保釈中に逃亡を踏みとどめるためのいわば担保の役目を持っており、刑事裁判での有罪・無罪関わらず、裁判が終わったときに返還されます。
保釈請求は被告人の家族が行うこともできますが、「裁判所のどこの部に出せばいいのか」、「なんの書面を提出すればいいのか」等、手続きには法的な知識や経験が必要です。
そのため、私選弁護人、もしくは国選弁護人に手続きをお願いすることが一般的です。
保釈請求が通らない場合、被告人は刑事裁判が終わるまでの期間、身柄拘束されたままになります。
起訴から初公判までは、事案にもよりますが大体1か月半から2か月程度、また初公判から判決までは2週間程度と考えられています。
そのため逮捕から判決がくだるまでずっと身柄拘束をされていたときには、おおよそ3か月程度身柄拘束されてしまうことになるのです。
さらに、刑事裁判となった場合、99パーセントが有罪判決となります。
執行猶予がつけば、身柄解放されますが、実刑判決となった場合さらに長期間受刑者として刑務所に収監される可能性があるのです。
逮捕された場合、早期に弁護士へ依頼すれば、身柄拘束される期間が短くできたり、不起訴処分を得られたする可能性が高くなります。
反対に、何も対応を行わないと、長期にわたって身柄拘束されてしまうこともありますので、「早く日常生活に戻りたい」と思うのであれば、弁護士へ相談することをおすすめします。
「刑事事件の基礎知識ファイル」に関する新着記事
「刑事事件の基礎知識ファイル」に関する人気記事
カテゴリから記事を探すこちらから記事を検索できます
キーワードで記事を探す
新着記事
-

執行猶予とは 「執行猶予という言葉をニュースなどでよく耳にするけれど、執行猶予付きの有罪判決は執行猶予が付かない有...
-

あおり運転をしてしまった⁉:弁護士による法的対応ガイド 「あおり運転のニュースを目にすることがあるが、これまでの自分の運転行為はあおり運転に該当していないだ...
-

詐欺罪とは | 刑罰や有罪判決の影響をわかりやすく解説 詐欺罪とは何か?詐欺罪とは、刑法第246条に規定されている犯罪で、人を欺いて財物を交付させたり、財...
-

起訴とは|意味や起訴前後の流れ、対応方法を解説 「起訴という言葉を聞くことがあるけれど、具体的にはどういう意味なんだろう?」起訴という言葉そのもの...
-
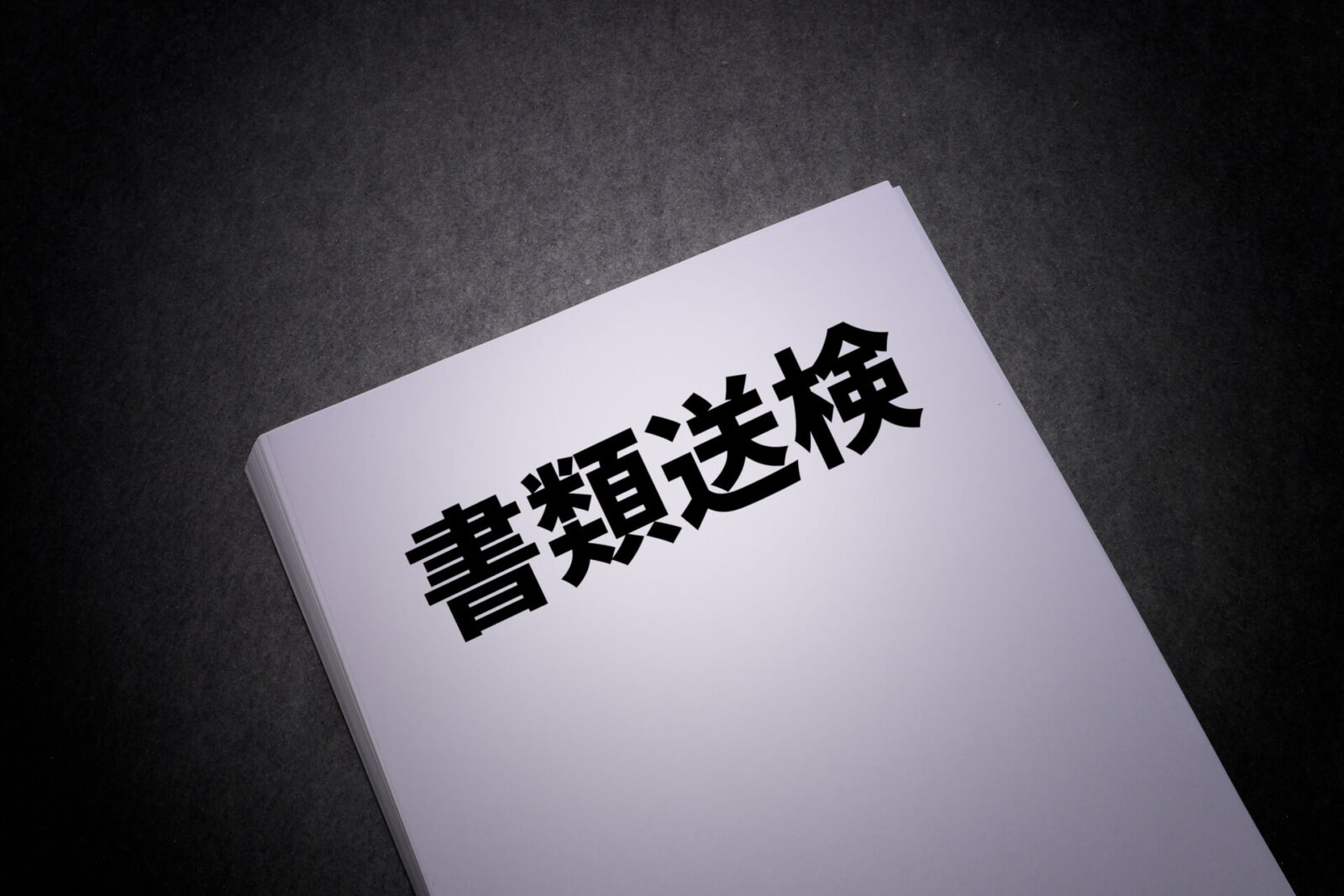
書類送検とは | 弁護士が導く安心ガイド テレビの報道などで、「名誉毀損の容疑で書類送検されました」といった言葉を耳にすることがあると思います...
人気記事
-
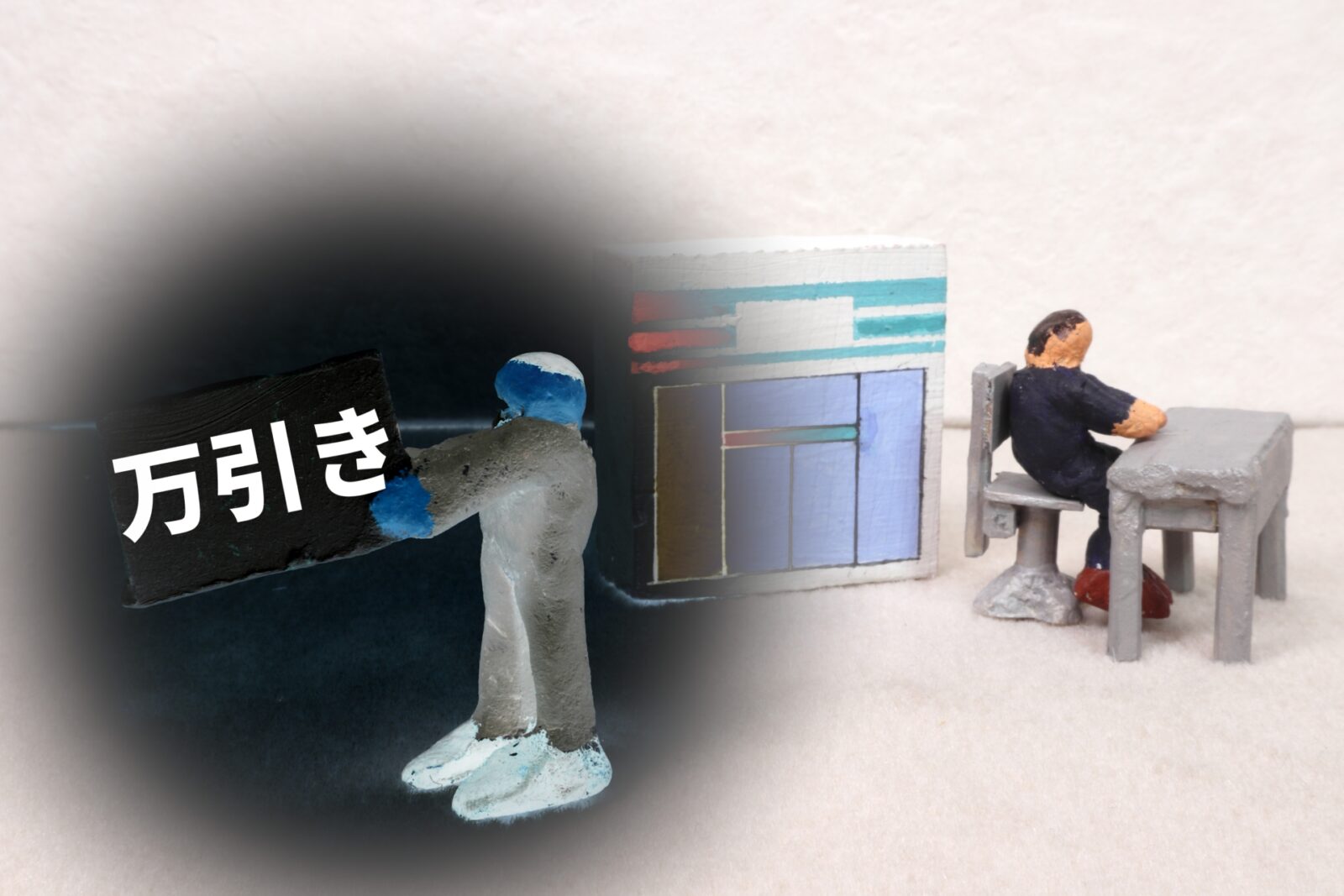
【弁護士監修】万引きで逮捕!?万引きしたらどうなる? 万引きは何罪になるのか万引きとは、買い物客のフリをしてスーパーやコンビニなどのお店から代金を払わず...
-
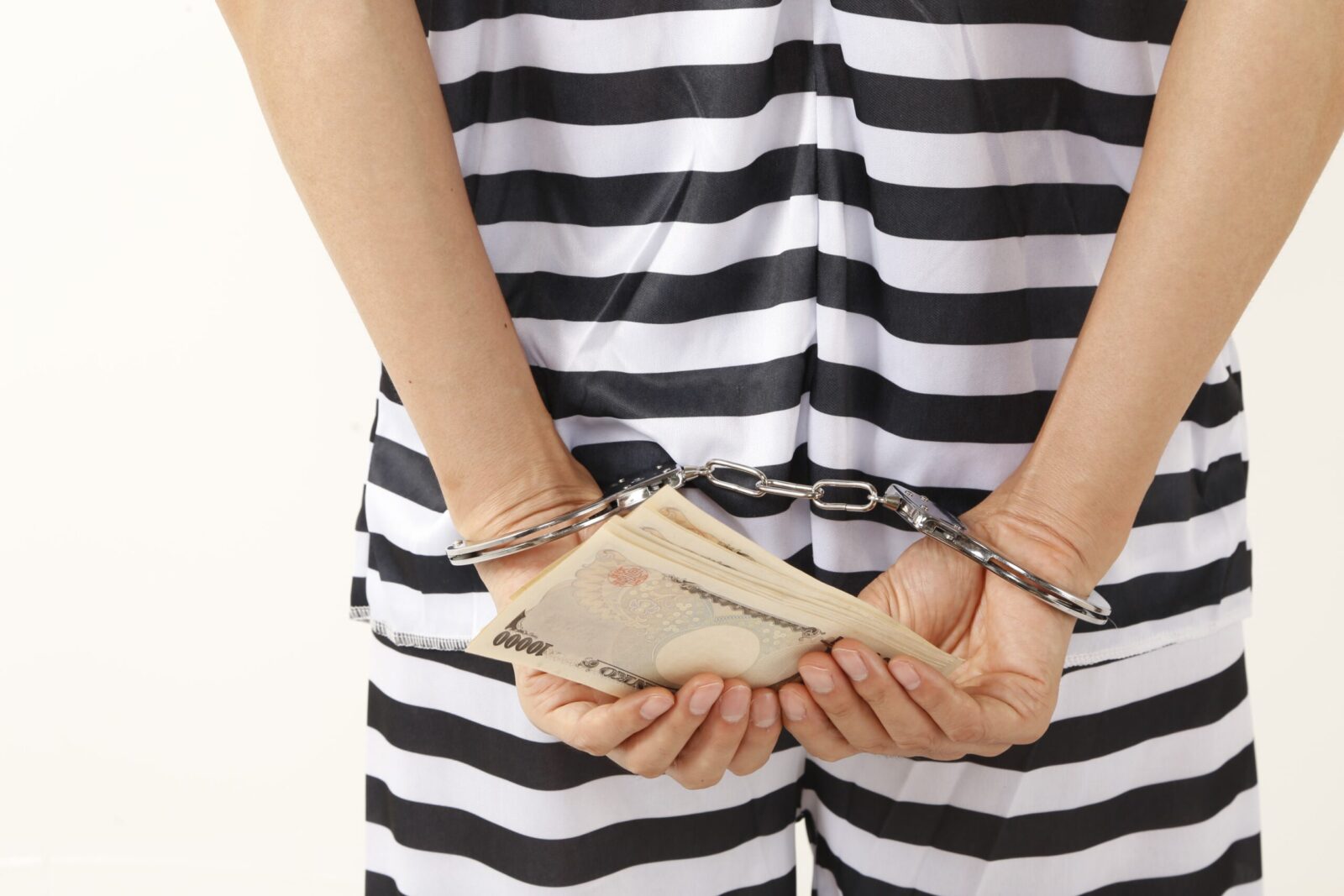
前科とはどんなタイミングでつくの?前科がつくデメリットとつかなくするための対処法とは? 一般的に前科がつくと、将来的にかなりの不利益を被るようなイメージがあります。とはいえ、どのようなタイ...
-

【逮捕されたら連絡は無理?】逮捕された家族と連絡を取るための方法を徹底解説 家族が逮捕された場合、最大72時間は面会したり、電話で連絡したりすることはできません。逮捕された家族...
-

【弁護士監修】逮捕と勾留の違いとは? 「逮捕」はニュース等でよく耳にする言葉ですが、「勾留」という言葉はあまりなじみがないという方も多いの...
-

【徹底解説】会社員が逮捕されたことを秘密にできるケースとは? 逮捕された場合、警察から会社に「従業員を逮捕した」と必ず連絡が来ると思う方もいらっしゃるかもしれませ...
近くの弁護士を探す




