恐喝罪が成立する条件とは?恐喝罪を犯したときに弁護士へ依頼するメリット
公開日2023/03/17
更新日2023/07/04
カテゴリ脅迫罪・恐喝罪

弁護士法人AO大橋 正崇弁護士
記事の監修者

恐喝罪とは、暴力や脅迫によってお金といった他人の財産を自分のものにする行為をいいます。
今回は、恐喝罪が成立する条件や罪を犯してしまったときに弁護士へ相談するメリットについて解説していきたいと思います。
【この記事のポイント】
- 恐喝罪が成立する条件を知ることができる
- 恐喝罪を弁護士に相談するメリットがわかる
恐喝罪はお金を脅し取ることで成立する罪
「恐喝」という言葉を聞いたとき、みなさんはどのようなイメージを持っているでしょうか?
殴ったり、胸ぐらをつかんだり、威圧感のあるひとが、「殴るぞ」と脅したりして、お金を巻き上げることを想像する方も多いと思います。
しかし、具体的にどのような条件で成立するのか、すぐに答えられる方は少ないでしょう。
さっそく恐喝罪が成立する条件を解説していきたいと思います。
恐喝罪が成立する具体的な条件を確認しよう
恐喝罪は、刑法249条で以下のように定められています。
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
条文から、恐喝罪が成立する条件は次のふたつに分けられます。
- 恐喝行為をしたこと
- 財物を交付させた、もしくは財産上不法な利益を得る、または他人にこれを得させた
1についてはイメージがつくかもしれませんが、2については、かなり難しいです。
それぞれ詳しく解説していきたいと思います。
恐喝行為をしたこと
恐喝行為とは、暴行・脅迫によって被害者の方を怖がらせて財産を交付させようとすることをいいます。
例えば、「金を出さないとぼこぼこに殴ってやる」といった言動や、相手を殴って、「金を出せ」といった行為が考えられます。
恐喝罪の暴行・脅迫は、「被害者の方の反抗を抑圧するには足らない」程度とされています。
少しわかりにくい言葉ですが、脅迫や暴行の内容が、被害者の方が反抗できる程度のものであったかということです。
この反抗できたかどうかの基準は、脅迫や暴行の度合いはもちろん、加害者・被害者の方の年齢や体格、性格、関係性等、状況によって大きく異なります。
なお、恐喝行為が被害者の方にとって、「反抗を抑圧する程度だ」と判断された場合、恐喝罪ではなく、強盗罪が適用される可能性があります。
強盗罪は、恐喝罪よりも刑罰が重く、有罪となった場合、5年以上の有期懲役なので、基本的に執行猶予が付きません。
そのため、恐喝行為が被害者の方の反抗を抑圧する程度かどうかはとても重要なのです。
財物を交付させた、もしくは財産上不法な利益を得る、または他人にこれを得させた
恐喝罪は、暴行や脅迫等を用いて、以下のいずれかの行為をする必要があります。
■財物の交付
財物の交付とは被害者の方を脅してお金を奪い取るようなことが考えられます。
■財産上不法な利益を得る、または他人にこれを得させた
また、飲食店等の店員を脅して無銭飲食をしたり、本来お金を支払って受けるべきサービスを脅迫や暴行を用いて、無償で受けさせたりするような行為についても、「財産上不法な利益を得」たとして、恐喝罪が適用される可能性があります。
また、「財産上不法な利益を得」た例としては、脅迫や暴行を用いて、相手に借金をさせたり、反対にお金を貸してくれたひとを脅して借金をチャラにしてもらったりするような行為があります。
恐喝罪は「未遂罪」が適用される
恐喝罪は、「他人を脅迫や暴行し、金銭等を強要した」時点で未遂罪が成立します。
つまり実際に、金銭等の財産を受け取っていなくても、恐喝行為をした時点で犯罪になりえるのです。
恐喝罪を犯した場合に科される刑罰を知ろう
恐喝罪について規定する刑法第249条では、「人を恐喝して財物を交付させたものは、10年以下の懲役に処する」と規定されています。
そのため、恐喝罪を犯した場合には10年以下の懲役刑のみが科され、罰金刑等は科されないこととなります。
恐喝罪を犯したときに弁護士に依頼するメリット
恐喝罪を犯してしまった場合、何もしないでいると検察官に起訴されて、有罪になってしまう可能性が高くなります。
仮に不起訴となった場合でも、逮捕・勾留された場合、留置場に拘束されるので、精神的に大きな負担を抱えてしまうことになるでしょう。
そのため、「恐喝してしまった」、もしくは「恐喝を疑われている」といった場合には、まず刑事事件に精通した弁護士への相談を検討してください。
さっそく、弁護士に依頼するメリットについて解説していきたい思います。
加害者にとって適切なアドバイスをくれる
恐喝罪を犯してしまった場合に本人が取り得る対策は複数存在します。
その中で、何よりも第一に被害者の方へ謝罪を行い、恐喝行為による被害を弁済するとともに、その他の慰謝料を支払うことができないか確認する必要があります。
そして、こうした謝罪や被害弁済を通じて恐喝事件についての示談交渉を行い、示談の成立を目指す必要があります。
こうした示談交渉が必要となるのは、それが本人にとって最大のメリットとなるからです。
具体的には、示談があったから必ず不起訴処分と認められることはありませんが、本人の起訴不起訴を裁判官が考慮するうえで示談の有無は大きな考慮要素となり得ます。
更に、仮に起訴されてしまったとしても、被害者の方との示談が成立しており、被害者の方に処罰感情が少ないことは、その判決を情状酌量により執行猶予などへ減刑させることへとつながります。
また、仮に示談交渉につき被害者の方が謝罪も慰謝料も拒絶され、交渉が全く進展しないような場合にも、弁護士として取りうる手段はあります。
具体的には、示談交渉を急ぐのでなく、じっくり時間を置いてから被害者の方の主張を最大限汲み取り、示談内容に反映させることが考えられます。
またそれ以外にも、法務局に対し示談金に相当する供託金をおさめ、被害者の方が供託金をいつでも受け取れるようにすることで、示談金を収めたのと同様の効果を期待することも可能です。
そのため、このような謝罪を通じた示談交渉や様々な対応は必要不可欠であり、本人の身柄拘束期間中、示談交渉や様々な対応をサポートできる弁護士もまた、必要不可欠といえるのです。
加害者の不利益が最小限に抑えられるように行動してくれる
恐喝罪で逮捕された場合、加害者本人は警察で最大48時間の身柄拘束を受け、その後検察へと身柄が送致されます。
そして、検察で最大24時間の身柄拘束を受けたのち、検察が裁判官へと勾留請求を行い、勾留請求が認められた場合には、原則10日以内、延長された場合には20日以内の身柄拘束を受けます。
この中で、弁護士として本人を身柄拘束から解放させる機会が複数存在します。
具体的には、以下のような場合です。
- 検察へと送致される段階
- 検察の身柄拘束段階
- 勾留請求を行う段階
- 起訴された後の段階
①②については、それぞれ司法警察員および検察官に対し、勾留要件を満たさないことを主張します。
具体的には、犯罪の嫌疑が薄い、定まった住所があるために逃亡の恐れが無い、罪証隠滅の可能性が低い、心身の状態が悪い等の理由で勾留の必要性がないなどといったことを主張することが考えられます。
③については、検察官からの勾留請求を受け裁判官が勾留の必要性を判断しますが、この勾留の判断をする裁判官に対して釈放を訴えます。また、裁判官のした勾留決定に対し準抗告を行うことも考えられます。
④について、起訴後の釈放を行う制度を「保釈」といいます。保釈とは、保釈保証金を納付する代わりに勾留から身柄を解放される制度をいいます。
保釈の可否については、被告人に「権利」としての保釈が認められる「権利保釈」(刑訴法89条)の要件を満たさない場合には、「裁量保釈」(同90条)の可否が問題となり、過去の犯罪歴や罪証隠滅の可能性、常習性、氏名や住居の有無などの事情に基づいて、裁判所の裁量によって保釈が許可されます。
弁護士としては、こうした本人の身柄拘束開放の機会を逃さずに、身柄拘束開放の必要性について各所に訴え、早期釈放、保釈を目指していくこととなります。
刑事弁護に精通する弁護士であれば、どのような主張が身柄の釈放に直結するかを熟知しています。
そのため、本人の身体拘束の不利益を最小限とするには、弁護士を利用することが必要不可欠なのです。
弁護士は加害者の立場にあっても必ず味方してくれる
弁護士の職務とは、依頼者が犯罪をした、しないにかかわらず、依頼者の望む結果を最大限実現することにあります。
そして、弁護士はその職責として、その依頼者が最大限の利益を実現できるよう、多様な法的観点から様々なアプローチを行い、努力します。
これに加え、国選弁護人と異なり、私選弁護人であれば、本人やその家族が信頼して弁護活動を依頼することとなります。
そのため、本人と信頼関係を構築しやすく、本人が恐喝事件と向き合い、その問題を乗り越えるまでの最大の味方とすることが可能となるのです。
まとめ
恐喝罪は行為者が被害者の方へ強烈な畏怖・恐怖のイメージを与えてしまう犯罪だからこそ、その事件の解決についても行為者本人が行うのでなく、弁護士という外部の人間が介在してこれを行うことが重要なこととなります。
恐喝事件の解決についてお悩みの方は、弁護士へご相談いただくことをおすすめいたします。
この記事の監修者

弁護士法人AO大橋 正崇弁護士
第一東京弁護士会
刑事事件は初動が非常に重要です。
弁護士に相談するかどうか迷っているうちに長期的な身柄拘束、また起訴されるリスクが高くなります。
弁護士法人AOは、刑事事件でお悩みの方のお話をしっかり伺い、被る不利益が最小限に食い止められるよう尽力いたします。
お困りの方は、ご相談ください。
弁護士法人AO
https://ao-law.or.jp/personal/
https://ao-law.or.jp/media/
「脅迫罪・恐喝罪」に関する新着記事
「脅迫罪・恐喝罪」に関する人気記事
カテゴリから記事を探すこちらから記事を検索できます
キーワードで記事を探す
新着記事
-

執行猶予とは 「執行猶予という言葉をニュースなどでよく耳にするけれど、執行猶予付きの有罪判決は執行猶予が付かない有...
-

あおり運転をしてしまった⁉:弁護士による法的対応ガイド 「あおり運転のニュースを目にすることがあるが、これまでの自分の運転行為はあおり運転に該当していないだ...
-

詐欺罪とは | 刑罰や有罪判決の影響をわかりやすく解説 詐欺罪とは何か?詐欺罪とは、刑法第246条に規定されている犯罪で、人を欺いて財物を交付させたり、財...
-

起訴とは|意味や起訴前後の流れ、対応方法を解説 「起訴という言葉を聞くことがあるけれど、具体的にはどういう意味なんだろう?」起訴という言葉そのもの...
-
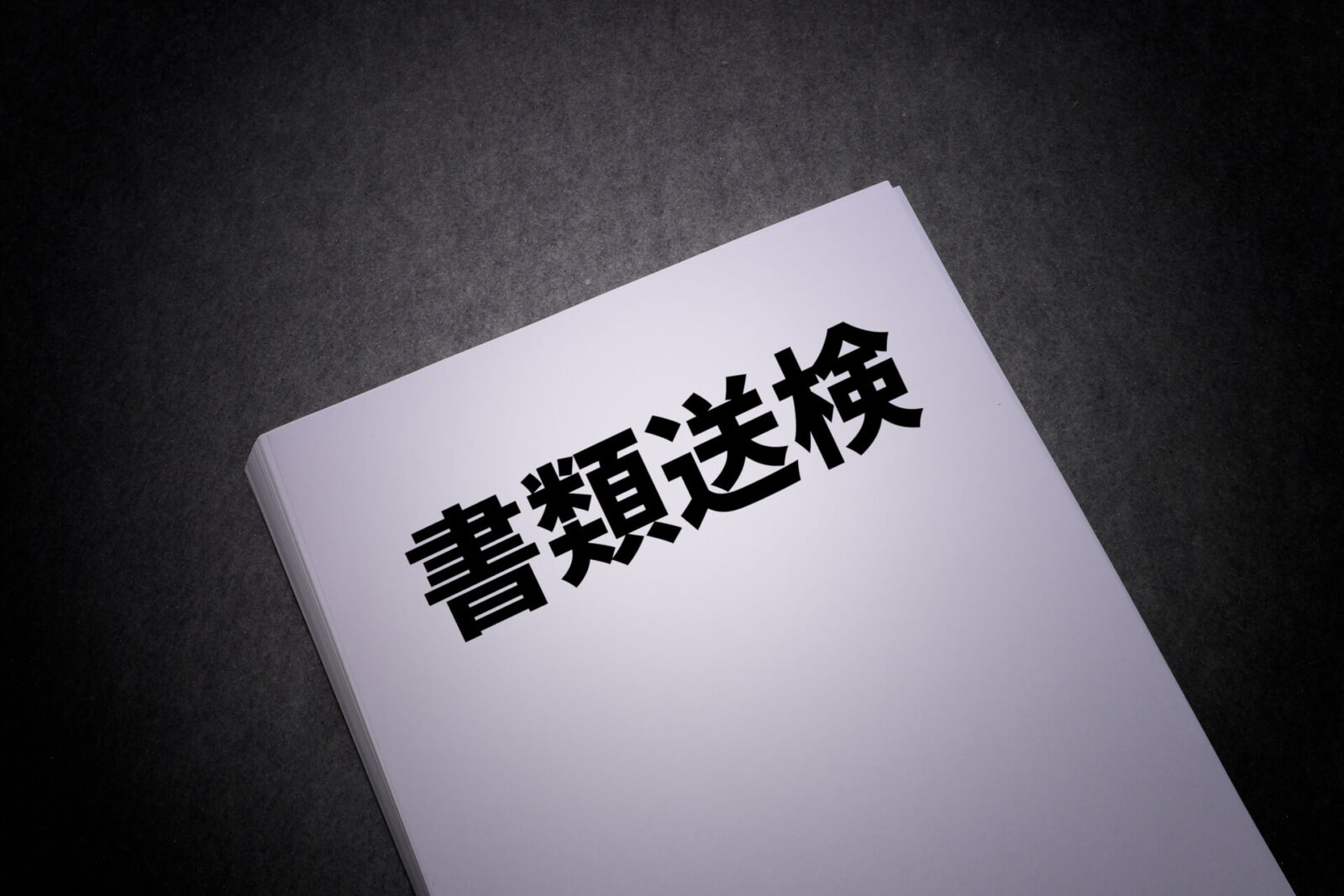
書類送検とは | 弁護士が導く安心ガイド テレビの報道などで、「名誉毀損の容疑で書類送検されました」といった言葉を耳にすることがあると思います...
人気記事
-

詐欺罪とは | 刑罰や有罪判決の影響をわかりやすく解説 詐欺罪とは何か?詐欺罪とは、刑法第246条に規定されている犯罪で、人を欺いて財物を交付させたり、財...
-

刑事事件の対処方法とは? 刑事事件の加害者となってしまった場合、逮捕されたり、逮捕はされなくても警察から任意同行など捜査の協力...
-

あおり運転をしてしまった⁉:弁護士による法的対応ガイド 「あおり運転のニュースを目にすることがあるが、これまでの自分の運転行為はあおり運転に該当していないだ...
-

刑事処分:知っておくべきこと、弁護士の役割 「刑事処分」とは何か?刑事処分とは、刑事事件の手続きの中で捜査機関によってなされる処分、そしてその...
-

弁護士への依頼した場合にかかる費用を知ろう! 弁護士に刑事事件の弁護を依頼した場合、具体的にどのような費用がかかるのでしょうか。弁護士の報酬規程...
近くの弁護士を探す
