大麻所持で逮捕 刑罰と解決までの流れ、弁護士の役割
公開日2023/07/27
カテゴリ薬物・覚せい剤・麻薬

大麻所持の罪で捕まるケースとしては、職務質問から所持が発覚し、そのまま現行犯として逮捕される場合が多くなっています。
ここでは、逮捕後に裁判を経て有罪となった場合の刑罰や解決までの流れ、そしてその中で弁護士が果たす役割について詳しく解説していきます。
大麻所持の刑罰とリスクとは?
まずは大麻の所持で有罪となってしまった場合にどういった刑罰を受けることになるのか、種類と内容についてみていきます。
大麻所持で逮捕されるとどんな刑罰が待っているのか?
大麻については所持、栽培、輸出入などが犯罪として大麻取締法に規定されています。
そして列挙された行為について、営利目的、つまり利益を得ることを目的として行っていた場合にはより重く処罰されることとなっています。
大麻所持の刑罰は、営利目的がない場合には5年以下の懲役、営利目的がある場合には7年以下の懲役および200万円以下の罰金とされています。
懲役とは判決で言い渡された期間の間、刑務所で身体拘束を受けながら刑務作業を行う刑であり、罰金は判決として言い渡された金額の金銭を納付する刑となります。
営利目的の場合には条文上「及び」という文言となっているため、懲役刑と罰金刑の両方を科されることがありうることになります。
実際に有罪率ってどれくらい?
逮捕や取り調べといった捜査を経て、刑事裁判に至った場合に、有罪判決を言い渡される割合を有罪率といいます。
ここでは、大麻所持事件の有罪率についてみていきます。
大麻所持の有罪率はどのくらいなのか?
刑事事件一般についての有罪率は、日本では罪を犯したことが確実といえるような場合しか検察官が起訴しないため99%以上とされています。
大麻事件の場合、所持だけでなく栽培なども犯罪とされており、法務省が公表する警察白書ではそれらの行為をまとめて大麻事件としてのデータしか公表していないため、大麻所持に限った有罪率は分かりません。
しかし、大麻事件としてでは、令和4年の犯罪白書によると2273人中2270人が有罪となっており、約99.87%が有罪となっていることが分かります。
そのため大麻所持に限った場合も99%を超える有罪率であると考えられます。
量刑軽減の可能性はあるの?
大麻所持の場合、5年以下の懲役といった刑罰を受けるおそれがあることは上述のとおりですが、ここではその刑罰が軽減される可能性があるのかについてみていきます。
量刑を軽減させる方法と条件
結論から言うと、大麻所持の罪で受ける刑罰を軽減できる可能性はあります。
軽減するために有効な方法としては、常習性がないこと、営利性が低いこと、共犯者がいる場合には従属的な立場であったことを示すことが挙げられます。
常習性がないことを示すということは、継続的に大麻を使用してきたわけではなく、また再犯のおそれも低いことを説明していくことになります。
具体的には初犯であることや薬物の入手ルートとなった関係者とのつながりを絶ったこと、さらには再犯防止のために治療を受けるなどしていることを示していくこととなります。
営利性が低いことを示すことは、営利目的であったとしても、大麻を所持していた量が少ないことを証明していくという方法になります。
共犯の場合には、共犯者に迫られて所持せざるを得ない状況に至ってしまったこと、具体的には組織の内部において弱い立場であったことや、弱みを握られる、脅迫されるなどして所持することになってしまったことを説明していくことになります。
逮捕から解決までの流れとは
ここまでは、逮捕され、さらに起訴された後の刑罰についてみてきましたが、ここからは実際に逮捕されてから解決に至るまでの流れについてみていきます。
大麻所持で逮捕されたらどんな流れになるのかわかりやすく解説
逮捕された場合には、被疑者(俗にいう容疑者)と呼ばれるようになり、まずは警察によって最大48時間身柄拘束されることになります。
そして警察の身柄拘束に引き続いて、身柄と事件に関しての書類が検察官に送られることになります。
これを報道などでは送検といいます。
検察は送検から24時間以内に被疑者を釈放するか、さらに身柄拘束を継続するよう裁判所に請求するか(これを勾留請求といいます。)の判断をします。
勾留される場合、その期間は原則10日間とされ、さらに10日以内の期間で勾留が延長されることもあります。
勾留期間が満了するまでに検察官は起訴するか不起訴とするか判断します(勾留期間満了までに判断がつかない場合には、処分保留として釈放されることになります。)。
起訴された場合には、刑事裁判を受けることになります。
この過程において、弁護士に弁護活動を依頼すると、逮捕や勾留によって身柄が拘束されている場合には、身柄の解放に向けた活動をすることになります。
具体的には、勾留は逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に限り行われることになるため、そのおそれがないことを説明します。
悪影響の大きい身柄拘束を解き、身柄拘束をされず、適宜呼び出しを受けて取り調べを受ける在宅事件として処理されるように動くことが、まず逮捕・勾留の段階での対応となります。
これに並行する形で、被疑者に有利な事情を説明し、不起訴処分にするよう働きかけていきます。
具体的には、家族や治療施設を準備するなどすることで、刑罰による更生ではなく、社会の中で更生していくことが適切であることを説明していくこととなります。
不起訴処分であれば前科がつくことはないため、大麻所持事件自体の解決となります。
起訴されてしまった場合には、有罪率の高さもあるため、主に量刑の面で有利な判決を求め、可能であれば執行猶予付きの判決を求めていくことになります。
大麻所持で逮捕されないためのポイント

大麻事件の場合には、逮捕された人の97%以上の人が実際に勾留されており、身柄拘束が長期間に及ぶことが確実といえます。
そのため、逮捕や勾留は、拘束期間、そして自身では外部と連絡をつけることもできないことから非常に悪影響の大きい状況といえます。
逮捕されないようにするためには、自身に逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを説明していくことが必要となります。
具体的には所持の疑いをかけられた場合に任意同行に素直に応じ、誠実に対応すること、そして逮捕される前の段階から弁護士に相談し、逮捕しないよう捜査機関に働きかけをしてもらうことがポイントとなります。
弁護士に頼まなくても大丈夫?
大麻所持で逮捕されてしまった場合、弁護士に依頼すると費用が掛かってしまうことになります。
ここでは弁護士に依頼しなくとも有利な処分を得られるかについてみていきます。
弁護士に頼まなくても無罪になれる可能性はある?
弁護士に依頼しなかった場合でも、不起訴処分を得たり、裁判で無罪判決を得たりする可能性は確かにあります。
しかし、有罪率を踏まえると裁判に至ってしまった場合には無罪判決を勝ち取ることは極めて困難です。
また、裁判に至らないようにするためには起訴されないこと、つまり不起訴処分を得ることが不可欠ですが、弁護士に頼まなければ外部との連絡手段もないため、社会生活を送りながら更生するという道を探すことも難しく、不起訴処分も得られにくくなります。
大麻所持で逮捕されたら弁護士って何をしてくれるの?
大麻所持事件で逮捕された場合の弁護活動は大きく「精神的サポート」と「法律的サポート」の2つに分けられます。
「精神的サポート」とは、逮捕によって孤独なまま取り調べに向き合わなければならない被疑者と直接話し、家族などからの連絡を伝え、できるだけ落ち着いて対応ができるようにすることをいいます。
逮捕されてしまった場合、被疑者は家族であっても面会することが許されず、その後の勾留の期間でさえ時間が限られ、場合によっては接見禁止となり、面会が一切許されないということもあります。
そうした中であっても、弁護士であればその弁護人としての立場から原則として自由に面会することができ、家族や友人と被疑者の間に立って連絡を取り次ぐことができます。
「法律的サポート」とは、被疑者に法的なアドバイスをする、弁護活動を行うといった活動をいいます。
被疑者が取り調べを受ける際、弁護士などが立ち会うことはできず、1人で対応しなければなりません。
そこで、どういった対応をすればいいのか、どういったことに注意しなければならないのかといったアドバイスを法律の専門家である弁護士としての立場から行います。
加えて、家族や場合によっては薬物の治療施設などと話し合い、被疑者の社会復帰に向けた準備をし、身柄解放や情状酌量(酌量減軽)を図るための活動を行います。
「弁護士選び」ポイント
国選弁護人に依頼する場合でなければ、個人で弁護士を選んで弁護士を依頼することができます。
その弁護士選びの際に注意するポイントについて解説していきます。
自分に合った弁護士を選ぶためのポイント
弁護士を選ぶ際に最も重視すべきポイントは弁護士との相性です。
弁護士に弁護活動を依頼する場合の契約関係は委任契約という依頼人と弁護士の信頼関係を基礎とする契約となります。
この委任契約を結び、取り調べの対応のアドバイスや、身柄解放に向けた弁護活動や法廷弁護活動を任せるためには、互いを信頼する必要があります。
接見でのコミュニケーションを通じ、事件についてすべてを話し、対応の一切を任せてもいいと思えるかが弁護士選びのポイントとなります。
相性以外でポイントとなるのが費用と弁護士の経験・強みとなります。
弁護活動を依頼した場合には、弁護士費用を支払う必要があります。
弁護士費用の着手金や報酬体系の金額は弁護士によってさまざまです。
実際に依頼する場合、どの程度の費用がかかるのかも知っておかなければなりません。
加えて、刑事事件では相手方は警察や検察といった国家権力となります。
その国家権力を相手にして対等に戦えるだけの経験があるか、刑事事件の弁護活動を強みとしている弁護士であるかという点も非常に重要なポイントとなります。
この記事の監修者

弁護士法人エースパートナー法律事務所市川 知明弁護士
■神奈川県弁護士会
刑事事件は、いつ弁護士に依頼するかによって、対応の幅が変わったり、不起訴処分や減軽の可能性が高くなったりします。
弁護士法人エースパートナー法律事務所は、逮捕段階・勾留段階、逮捕前のご相談も受け付けております。
「依頼者の方との絆”を大切に、迅速・適切・こまめなサポート」をモットーに日々尽力しておりますので、刑事事件でお困りの方はご相談ください。
「薬物・覚せい剤・麻薬」に関する新着記事
「薬物・覚せい剤・麻薬」に関する人気記事
カテゴリから記事を探すこちらから記事を検索できます
キーワードで記事を探す
新着記事
-

執行猶予とは 「執行猶予という言葉をニュースなどでよく耳にするけれど、執行猶予付きの有罪判決は執行猶予が付かない有...
-

あおり運転をしてしまった⁉:弁護士による法的対応ガイド 「あおり運転のニュースを目にすることがあるが、これまでの自分の運転行為はあおり運転に該当していないだ...
-

詐欺罪とは | 刑罰や有罪判決の影響をわかりやすく解説 詐欺罪とは何か?詐欺罪とは、刑法第246条に規定されている犯罪で、人を欺いて財物を交付させたり、財...
-

起訴とは|意味や起訴前後の流れ、対応方法を解説 「起訴という言葉を聞くことがあるけれど、具体的にはどういう意味なんだろう?」起訴という言葉そのもの...
-
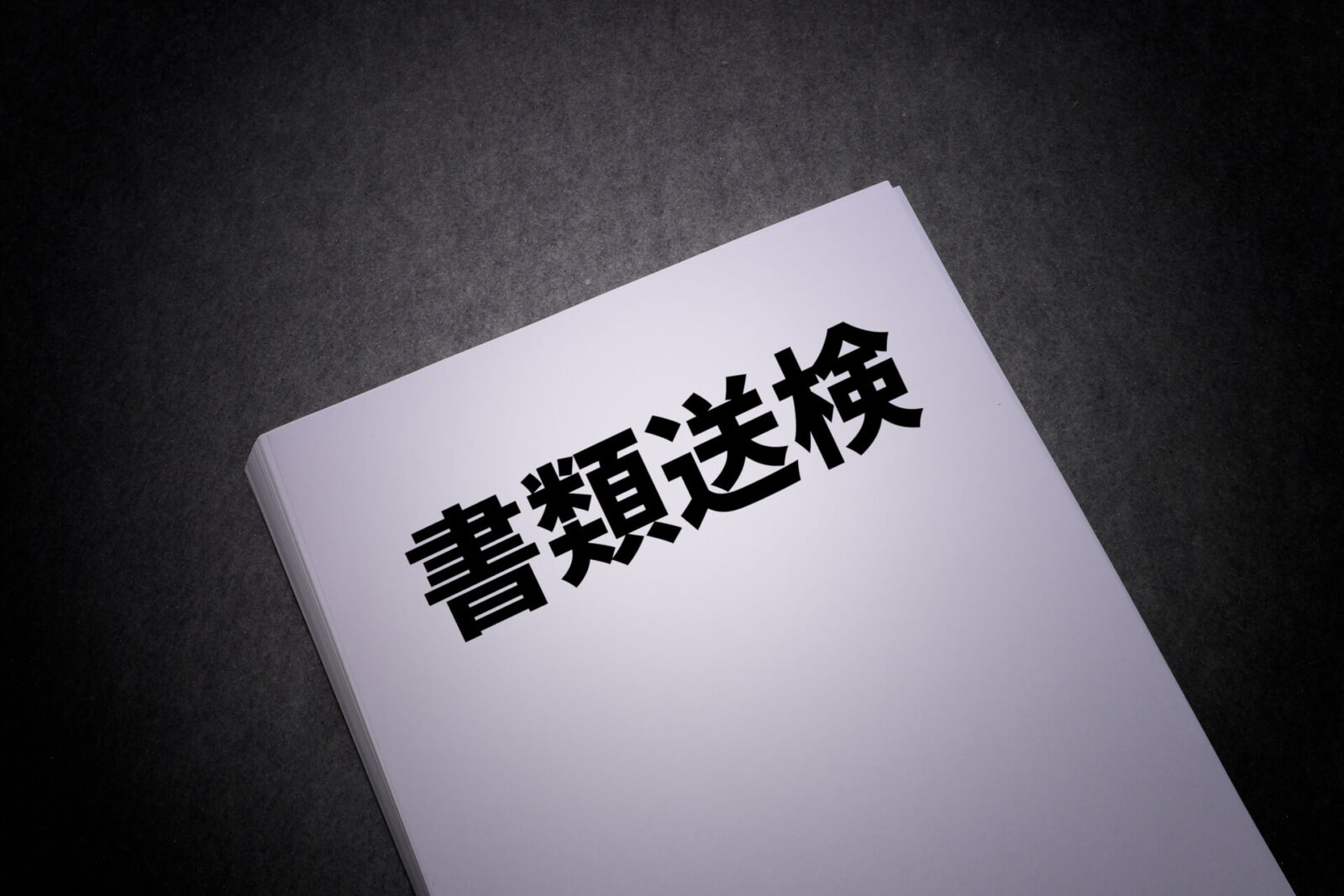
書類送検とは | 弁護士が導く安心ガイド テレビの報道などで、「名誉毀損の容疑で書類送検されました」といった言葉を耳にすることがあると思います...
人気記事
-

【弁護士監修】逮捕と勾留の違いとは? 「逮捕」はニュース等でよく耳にする言葉ですが、「勾留」という言葉はあまりなじみがないという方も多いの...
-

恐喝罪が成立する条件とは?恐喝罪を犯したときに弁護士へ依頼するメリット 恐喝罪とは、暴力や脅迫によってお金といった他人の財産を自分のものにする行為をいいます。今回は、恐喝...
-

【弁護士監修】刑事事件で示談するには?被害者と示談するメリットを知ろう 刑事事件で逮捕されてしまった場合、被害者との示談交渉をなるべく早めに成立させるべきと聞いたことはあり...
-

【弁護士監修】刑事事件の示談書は自分で作成できるのか? 刑事事件を起こしてしまった場合、被害者側と示談交渉を行うことが少なくありません。被害者側との示談交...
-

人を殴ってしまった!傷害罪で慰謝料等を支払わないとどうなる?慰謝料等を支払わないままでいると生じるリスクとは? 傷害事件を起こしてしまった場合,被害者に対して慰謝料等の損害賠償金を支払う責任を負うことになります。...
近くの弁護士を探す